2006年4月3日より一次予選を通過した18名による二次予選が行われました。そして、4月8日、第一回東京芸術センター記念ピアノコンクール本選が開催され、同4月9日に入賞者発表・入選者披露演奏会が執り行われました。
1次予選から数多くの応募を頂き、誠にありがとうございました。


東京芸術センター
記念賞
賞金50万円
金賞
賞金40万円
松本 伸章 さん
東京音楽大学
1999年宮崎県高校独唱・独奏コンクール金賞・グランプリ受賞。
同年第23回全九州高校音楽コンクールで金賞受賞。
2003年第22回飯塚新人コンクール1位。
2004年第3回東京音楽大学コンクール2位。
2006年第1回東京芸術センター記念ピアノコンクール金賞・東京芸術センター 記念賞受賞。

銀賞
賞金30万円
長嶋 未来 さん
東京音楽大学
2001年第2回ローゼンストック国際ピアノコンクール審査員特別賞受賞。
2002年第4回21世紀ピアノコンクール3位。
同年第13回彩の国埼玉ピアノコンクール銅賞受賞。同年第28回 ピティナ・ピアノコンペティションG級入選。
2006年第1回東京芸術センター記念ピアノコンクール銀賞受賞。

銅賞
賞金20万円
遠山 沙織 さん
桐朋学園大学研究科
2003年やちよ音楽コンクール1位。
2006年第1回東京芸術センター記念ピアノコンクール銅賞受賞。

感動賞
賞金10万円
関屋 まき さん
モスクワ国立音楽院
1990年セニガリヤピアノコンクール(ジュニア)1位。1991年マリア・カナルスピアノコンクール(ジュニア)3位。
2001年トビリシピアノコンクール5位。
2003年ギレリスピアノコンクール6位。
2003年ザイラーピアノコンクール1位。
2006年第1回東京芸術センター記念ピアノコンクール感動賞受賞。

河野 泰子 さん
東京芸術大学大学院
2006年第1回東京芸術センター記念ピアノコンクール入選。

和田 由布子 さん
桐朋学園大学音楽学部
2002年ペトロフピアノコンクール審査委員賞。
2003年第4回北関東ピアノコンクール2位。
2004年第4回彩明ムジカピアノコンクール3位。
2006年第1回東京芸術センター記念ピアノコンクール入選。
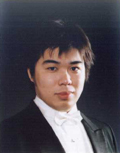
安齊 周 さん
武蔵野音楽大学大学院
2002年第8回P.I.A.Japan音楽コンクールAクラス2位。
2003年第13回日本クラシック音楽コンクール大学生の部最高位。
2005年カワイ・クラシックオーディションピアノ独奏部門最優秀賞。
同年11th INTERNATIONAL PIANO COMPETITION "KONZERTEUM '05"第2位(1位なし)、クラシックソナタ賞。
2006年第1回東京芸術センター記念ピアノコンクール入選。

手嶋 麻子 さん
ニューイングランド音学院
1989年PTNAピアノコンペティションC級ベスト賞受賞。
2002年堺国際ピアノコンクール入賞。
同年レ・スプレンデル音楽コンクール2位。
同年ベストプレイヤーズコンテスト審査員賞受賞。
2006年第1回東京芸術センター記念ピアノコンクール入選。

小熊 一輝 さん
東京音楽大学大学院
1992年毎日こどもピアノコンクール金賞。
2006年第1回東京芸術センター記念ピアノコンクール入選。

東京芸大音楽学部卒業
マックス・エッガー教授マスタークラス
及びコンサートクラス修了。演奏家と
して活動する傍ら大学で指導も行う。
演奏者の健闘を称えます。コンクールに臨む真摯な態度と素敵な資質や個性が垣間見える演奏。好感を持つと同時に責任の重みを痛感致しました。審査の際には、技術・音楽性・音色や響きをコントロールする感性・楽曲への理解・芸術性を大切なポイントと考えつつ、総合的に判断致しました。今後共に、皆様の更なる御活躍を期待しております。

国立音大卒業。
チャイコフスキー記念
国立モスクワ音楽院修了
日露芸術交流支援・ピアノ奏法指導
ノーティ音楽アカデミー代表。故L.ナウ
モフに師事カシオキーボードCMにも
出演
審査員公募という珍しい形態のこのコンクールは、純粋に音楽と演奏を評価し、またクラシックピアノ音楽の底力を魅力的に開示した。今回審査をさせていただいた中で、舞台でのパフォーマンスは、音やフレーズ間はもとより曲の合間でさえ聴衆を魅了する指や体の動きというものが心に届く演奏につながるのだと感じる事ができた。次回もとても楽しみである。
桐朋学園大音楽学部卒
業。ベルリン国立音大
ハンス・アイスラー卒業
日本、ドイツにてソリスト、室内楽奏者
としての活動の傍ら後進の育成にも力
を注ぐ。
全体的にやや色彩感に乏しい感は否めませんでしたが、技術的水準は大変高く、又、メンタルな面でのタフさも印象に残りました。惜しくも本選まで残れなかった出場者の中にも音楽的なセンスを備えた方々が見受けられ、非常に接戦であったと思います。近い将来、このコンクールから世界へ羽ばたく人材が育つことは間違い無いと確信しております。

アムステルダム音楽院卒業
ヴィレム・ブロンズ師事。ヨーロッパ各
国で演奏活動を行う。来日後は九州
交響楽団と共演他演奏活動を各地で
行う。大学・高校で「演奏法」と特別
レッスンを行う。
演奏者の音楽への深い理解と音楽性、情熱にポイントを絞って審査しました。技術評価に偏りがちな音楽コンクール審査の常識に一石を投じる結果だったかも知れません。今後も芸術性と公平性を最も重視する貴重な機会として、当コンクールがクラシックピアノ業界をリードする存在になって欲しいと願います。

武蔵野音大ピアノ科、国立
音楽院調律科卒業。
同院講師
トリニティ・カレッジ・ロンドン演奏家ディ
プロマ取得。日本フンメル協会会長、
ピアニスト、音楽ジャーナリスト。
第1次審査開始から本選終了まで審査員と出場者名が公表されず、先入観なくひたすら「音楽」に、純粋な心構えで向き合うという貴重な経験ができました。また、21世紀のピアノ界を担っていく若いピアニストたちが、ピアノ改良史の中で燦然と輝くベヒシュタインとプレイエルを演奏して競い合った饗宴は、ピアノ史の1ページを飾り、コンクール運営にも一石を投じたことを大変うれしく思います。